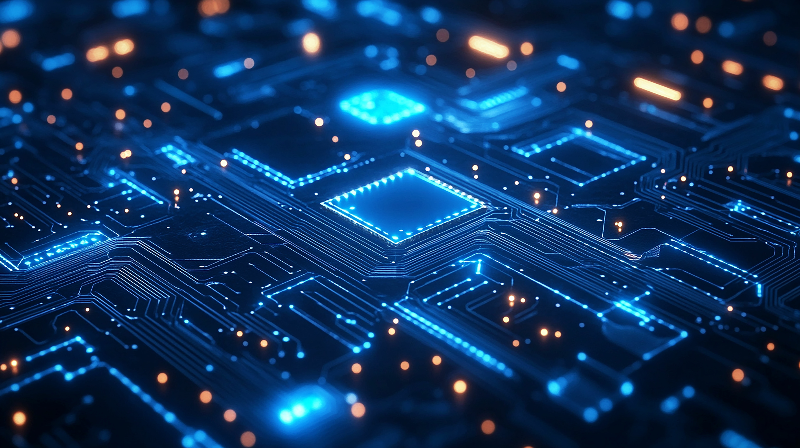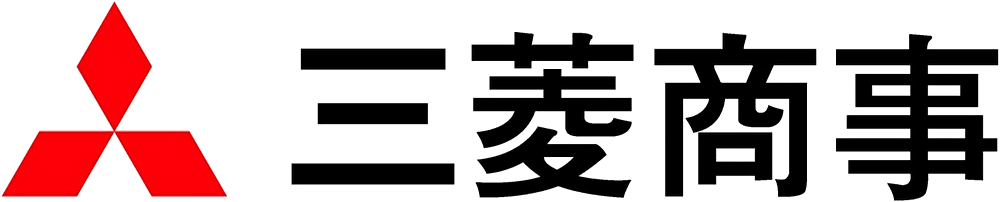パスキーとは?仕組みやメリット、活用時の注意点を解説

日々進化するサイバー攻撃に対抗するため、より安全で信頼性の高い認証システムを模索しているIT・セキュリティ担当者も多いことでしょう。その中で注目を集めているのが、パスワードを使用しない新しい認証技術「パスキー(Passkeys)」です。
セキュリティの強化やユーザー体験の向上が期待されていますが、「どのような仕組みで動作するのか」「導入時に注意すべき点はあるのか」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
本記事では、パスキーの仕組みやメリットに加え、導入を検討する際に押さえておきたいポイントについて解説します。
- 目次
パスキー(Passkeys)とは
パスキー(Passkeys)は、従来のパスワードに代わる認証方法です。すでに多くのデバイスやWebサービスで採用が進んでおり、今後さらに普及が期待されています。
まずは、パスキー認証の仕組み、パスワードや生体認証との違いについて解説します。
パスキー認証の仕組み
パスキーは「公開鍵暗号方式」を基盤とした高度なセキュリティ技術で、以下の手順で認証が行われます。
1.ユーザーがサービスに登録する
2.「公開鍵」と「秘密鍵」が生成される
3.公開鍵をサービスに、秘密鍵をデバイスに保存する
4.認証時に生体情報(顔・指紋)を利用する
5.デバイスが秘密鍵を使用して署名を生成する
6.サービス側が公開鍵で検証する(本人確認が完了)
デバイスで指紋などを認証し、サービス側では最終確認のみを行う仕組みのため、このプロセスにより、ログイン情報が第三者に盗まれるリスクが大幅に軽減されます。また、パスワードを記憶したり入力したりする必要もありません。
セキュリティと利便性を兼ね備えている点がパスキーの大きな特徴と言えるでしょう。
パスキーとパスワードとの違い
パスキーとパスワードを比較するために、まず認証に使用される3つの要素について説明します。
「知識情報(Something You Know / SYK)」は「ユーザーが知っていること」を指します。具体的にはパスワードや暗証番号、秘密の質問です。
「所有情報(Something You Have / SYH)」は「ユーザーが所有しているもの」です。例えばスマートフォンや社員証、キャッシュカードが挙げられます。
「生体情報(Something You Are / SYA)」は「ユーザー自身の身体的特徴」であり、指紋や顔が該当します。
従来のパスワード認証は「知識情報」のみを使用します。そのため、辞書攻撃や総当たり攻撃、ソーシャルエンジニアリングといった手法で簡単に突破されるという課題がありました。そこで、2012年にFIDO Alliance(ファイド アライアンス)が設立されました。この団体はオンライン認証技術の標準化を目指し、パスワードに頼らない認証方法「パスキー」を開発しました。
パスキー認証は原則として「知識情報」は使用せず、「所有情報」と「生体情報」の両方を使用します。複数の要素を組み合わせるため、「多要素認証(MFA)」の一種です。生体情報や所有情報を突破しない限りログインは不可能です。不正ログインやなりすましを効果的に防げるため、「Phishing Resistant MFA(フィッシング耐性のある多要素認証)」とも呼ばれています。
ただし、例外的に「PINコード(知識情報)」を利用するケースもあります。これは、所有情報(例: スマートフォン)のローカル環境でのセキュリティを強化する目的で用いられるものであり、パスキーの特徴である「パスワードに頼らない認証」を損なうものではありません。
パスキーと生体認証との違い
パスキーと生体認証は似ていますが、異なるものです。
生体認証は、指紋や顔、虹彩、声、静脈といった身体の特徴を用いて本人確認を行います。ただし、システムによってはこの情報が外部のシステムに送信されることもあり、その場合はサイバー攻撃によって生体情報が盗まれる可能性も否定できません。
一方、パスキーは生体認証やPINコードを利用するものの認証自体は秘密鍵で署名を生成し、公開鍵でその署名を検証する仕組みです。生体情報はユーザーのデバイス内でのみ使用され、サービス提供者側に送信されたり保存されたりすることはありません。そのため、パスキーは生体認証単体よりも高い安全性を備えているとされています。
パスキーが注目される背景
多くのWebサイトで利用されているID・パスワード認証は、ユーザーが事前に登録したIDとパスワードを使ってログインする仕組みです。しかし、推測されやすいパスワードや、複数のサイトで同じID・パスワードを使い回すケースが少なくありません。
このような状況が原因で、フィッシング攻撃やランサムウェアといった巧妙化するサイバー攻撃に対し、従来の文字ベースのパスワードでは防ぎきれないという課題が浮き彫りになっています。
こうした背景から、新しい認証方法として注目されているのが”パスキー”です。
最近のスマートフォンやパソコンには、生体認証機能(指紋認証や顔認証など)が標準装備されているため、パスキーへの移行が比較的スムーズに行えることも利点の一つです。
実際、すでにApple、Google、Microsoftといった大手企業が自社サービスに導入しています。
セキュリティリスクを減らしながら利便性を向上させたいとお考えであれば、パスキーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
パスキーのメリット
パスキーは、従来のパスワードに代わる認証方法として浸透しつつありますが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、パスキーならではの強みをご紹介します。
詐欺被害を減らせる
従来のパスワード認証では「フィッシング詐欺」「なりすまし」「総当たり攻撃」に弱いという特徴があります。
例えば、本物のWebサイトと見分けがつかない偽のページにIDやパスワードを入力してしまうと、攻撃者にその情報が直接送信され、不正アクセスに利用されてしまいます。
しかし、パスキーは生体認証や秘密鍵を組み合わせるため、攻撃者がたとえ公開鍵を入手してもログインは不可能です。特に、指紋や顔といった生体情報は複製が非常に困難であり、詐欺や不正アクセスのリスクを大幅に軽減することができます。
パスワードを覚える必要がない
パスキーでは生体認証(顔や指紋)またはPINコードを使用して認証を行うため、複雑なパスワードを覚える必要がありません。複数のサービスで異なるパスワードを使い分ける手間が省け、パスワード管理から解放されます。
また、生体認証を使うことでログイン操作が非常にスムーズになり、ストレスを感じることなく利用できます。
個人情報漏洩のリスクが減る
従来のパスワード認証では、サービス提供者側にパスワードやIDが保存される仕組みです。もしログイン情報が流出してしまえば、住所や名前といった個人情報も盗まれ、不正利用されてしまうでしょう。
しかし、パスキーでは公開鍵のみがサービス提供者側に保存され、秘密鍵はユーザーのデバイス内に留まります。このため、仮にサービス提供者側がサイバー攻撃を受けたとしてもログインできず、個人情報は保護されるのです。
複数デバイスで使える
パスキーはウェブやアプリなどのサービスを利用するとき、同じオンラインアカウントでログインしていれば、PC、スマートフォン、タブレットなど複数のデバイスで同期して利用することも可能です。例えばスマートフォンで作成したパスキーを、PCやタブレットでも使用できるため、場所やデバイスに関係なくスムーズなログインが実現します。
問い合わせが減る
パスキーを導入することで、パスワードに関するトラブルや問い合わせが減少するので、サポートの工数が削減できます。従来のパスワード認証では、「パスワードを忘れた」「パスワードをリセットしたい」「ログインできない」といった問い合わせが頻発し、サポート部門やパスワードの管理者側にとって負担となっていました。しかし、パスキー認証であればパスワードの入力ミスなどが起こらず、操作がシンプルで直感的なため、問題なくログインできるようになります。
パスキー導入時の注意点
パスキーはセキュリティと利便性の両面で優れた技術ですが、導入にあたってはいくつかの注意点があります。自社の利用環境や運用フローに適合するかを事前に確認しましょう。
対応しているアプリ・デバイスが限られる
パスキーは比較的新しい技術のため、すべてのアプリやデバイスで利用できるわけではありません。生体認証を利用するなら専用の機能を搭載したスマートフォンやパソコンが必要となるため、環境によっては導入が難しい場合があります。
特にB2C向けサービスを展開している場合、古いスマートフォンを使用している消費者(エンドユーザー)がパスキー認証に対応できないケースが考えられます。そのため、パスキーの導入を検討する前に、対象ユーザーのデバイス環境や利用シーンを十分に考慮することをおすすめします。
デバイス紛失時に悪用される危険性がある
パスキーは秘密鍵をデバイス内に保管する仕組みのため、デバイスを紛失した場合は悪用されるリスクがあります。
もちろん、生体認証やPINコードがセキュリティの壁となるため、第三者が簡単に利用することはできません。しかし、万が一の事態に備えて、利用サービスの設定画面から該当の端末を連携停止(削除)したほうがよいでしょう。
パスキー対応ID管理基盤のご紹介
パスキー認証は、セキュリティの強化と利便性の向上を同時に実現できる新しい認証方法として、多くの注目を集めています。しかし、複数のクラウドサービスを利用している場合はアカウントごとに設定が必要で、従来のパスワード認証が併用されるケースもあり、ID管理が煩雑になるという課題が残ります。
そこでおすすめなのが、大企業向けID管理基盤「LaKeel Passport」です。LaKeel Passportは、SaaSや既存システムのID管理を一元化することができます。
特に注目すべきポイントは、パスキー認証への対応です。LaKeel Passportでは、事前に登録した多段階・多要素認証を利用することで、簡単かつ安全にログインが可能になります。
企業の情報セキュリティ対策を次のレベルへ引き上げたい企業は、この機会にLaKeel Passportを検討してみてはいかがでしょうか。


このコラムを書いたライター

本サイトでは、企業のDX推進に役立つ様々な情報をお届けしています。