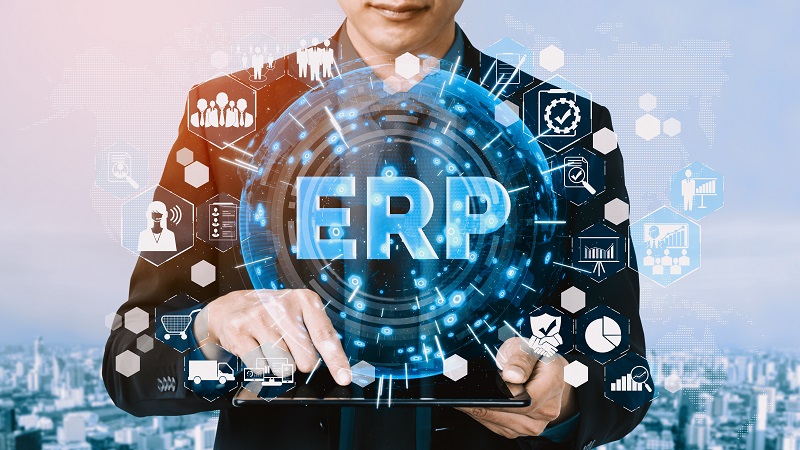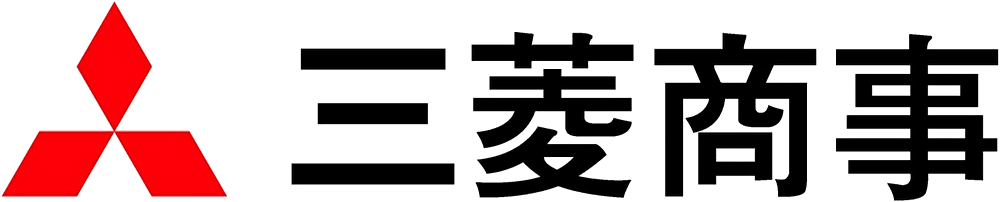Notes/Dominoのv9とv10の延長サポートはいつまで?
サポート終了後に気をつけるべきことと対処法とは

HCL Notes/Dominoのv9およびv10は、2024年6月に通常サポートが終了し、延長サポートも2026年6月までと期限が設けられています。
そのため2025年は、「バージョンアップか、他サービスへの移行か」を本格的に検討すべきタイミングと言ってよいでしょう。
しかし、十分な準備をしないままサポート期限を迎えてしまった場合、セキュリティトラブルや業務の一時停止といったリスクを抱える可能性も考えられます。
そこで本記事では、Notes/Dominoのサポート状況をはじめ、サポート終了後に想定されるリスク、そして今後取るべき対応策について解説します。
- 目次
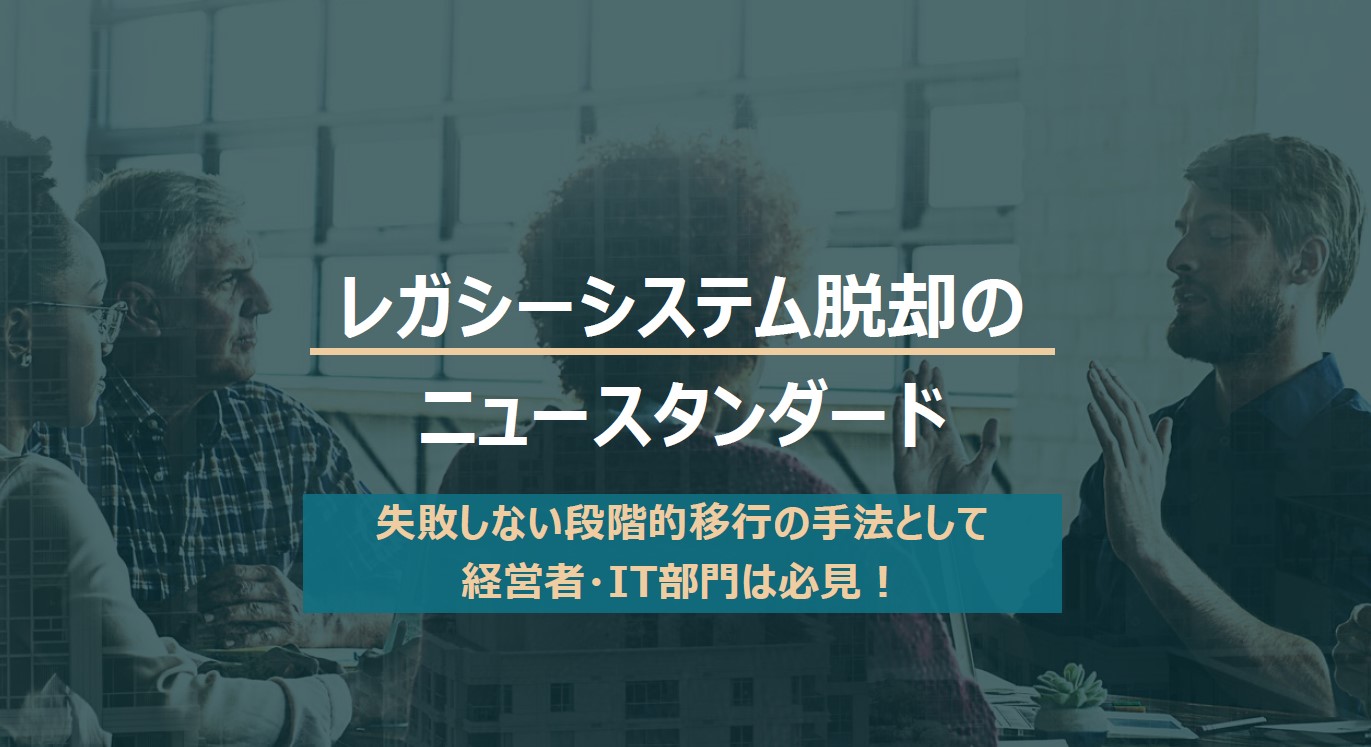
- お役立ち資料
- レガシーシステム脱却の
ニュースタンダード
Notes/Domino v9 と v10のサポート状況について(2025年4月時点)
HCL Notes/Dominoのサポート終了に関する情報はインターネット上で多く出回っていますが、すべてが正しいとは限りません。
中には「すべてのバージョンが使えなくなった」と誤った印象を与え、他社サービス(製品)への移行を強く勧めるような記事も存在します。
こうした情報に惑わされないためにも、信頼できるソース、つまりHCL Softwareが発信する情報を確認することが重要です。
実際、HCL 公式サイトには、v9.0.xおよびv10.0.xは2024年6月1日に通常サポートが終了するものの、延長サポート契約を結ぶことで2026年6月2日まで利用可能であることが記載されています。
また、v11.xについては通常サポートが2025年6月25日まで、その後は2026年6月26日まで延長サポートが用意されています。
v12およびv14(最新版)は現在も通常サポート中であり、サポート終了日は2025年4月9日時点で未定です。バージョンごとのサポート提供期間は以下のとおりです。
HCL Notes/Dominoのバージョン | 通常サポート終了日 | 延長サポート終了日 |
v9.0x | 2024年6月1日 | 2026年6月2日 |
v10.0x | 2024年6月1日 | 2026年6月2日 |
v11.0x | 2025年6月25日 | 2026年6月26日 |
v12.0.1、v12.0.2、v14.0 | 継続中(未定) | 未定 |
※v13は欠番となっており、存在しません。
参照:HCLSoftware|2024年10月14日更新: HCL Notes/Domino v9.0.x および v10.0.x の営業活動終了 (2022年12月1日) とサポート終了 (2024年6月1日) および延長サポート (2026年6月2日まで) について
サポート終了後に気をつけるべきこと
サポートが切れた状態でもシステムは動作しますが、セキュリティアップデートが受けられなくなり、サイバー攻撃に対して無防備な状態になります。
また、システム障害やトラブルが発生した際もベンダーからのサポートが受けられないため、迅速な復旧が困難になります。
延長サポート期間が設けられていても、「まだ時間がある」と先延ばしにするのではなく、早めに対応を検討することが重要です。
以下に、サポート期限切れによって発生しやすいリスクをまとめました。今後の対応を考えるうえで、ぜひ参考にしてください。
セキュリティリスクの急増
サポートが終了したソフトウェアは、不具合の修正や機能のアップデートが提供されません。
さらに、脆弱性(セキュリティホール)を修正するためのパッチ提供も受けられなくなるため、サイバー攻撃やマルウェアに対して無防備な状態で使い続けることになり、非常に危険です。
保存されたデータが盗まれたり、勝手に削除・改ざんされたりすれば、業務全体がストップするような深刻な事態に発展する可能性もあります。
万が一、個人情報や機密情報が漏えいした場合には顧客や取引先との信頼関係が損なわれるだけでなく、高額な損害賠償を請求されるケースも考えられます。
システム停止や復旧遅延
サポートが終了したソフトウェアでも引き続き使用することは可能ですが、経年劣化によって不具合や動作不良が発生しやすくなります。
かつては問題なく連携していた外部サービスやアプリも対応を終了し、次第に使える機能が制限されていくリスクもあります。
さらに、万が一トラブルが発生しても、サポートが切れたソフトウェアではメーカーからの問い合わせ対応や技術サポートを一切受けることができません。
自社で障害の原因を特定し、復旧する際には多くの時間と人手がかかってしまうでしょう。トラブル対応に時間を取られれば社内の業務は停滞し、顧客への対応遅延やサービス提供の停止といった影響も避けられません。
保守コストの増大
システム保守には高度な専門知識とスキルが求められるため、社内で対応できるケースは限られ、多くの企業ではシステム提供元であるベンダーやベンダー公認の委託会社に依頼していることでしょう。
しかし、先述の通り、サポートが終了したソフトウェアに対しては、障害対応や定期点検といったサポートが打ち切られてしまいます。
Notes/Dominoのように延長サポートが用意されていても、通常サポートと比べて割高になるのが一般的です。さらに、サポート対象外で修理や復旧を依頼する際には、高額な費用が発生する可能性があります。
また、ベンダーやベンダー公認の委託会社以外の業者が延長(延命)サービスや修理サービスを提供している場合もありますが、こちらもコストが跳ね上がってしまうのが予想されます。
サポートが切れたら他サービスへ移行が必要なのか?
サポート終了に直面した際、すぐに対応に踏み切れない企業も多いでしょう。予算の都合、人員の確保、既存システムとの互換性など、乗り越えるべき課題は少なくありません。
しかし、サポートが終了したソフトウェアを使い続けることには重大なリスクがつきまといます。
そのため、「同じサービス内でのバージョンアップ」もしくは「他システムへの移行」のいずれかを早い段階で決断することが重要です。
それぞれメリット・デメリットがあるため、自社のIT環境や業務プロセス、将来的な運用方針に合わせて慎重かつ迅速に判断しましょう。
以下に、バージョンアップと他システム移行について分かりやすく整理しましたので、ご参考ください。
同じサービスラインでのバージョンアップ
まず検討すべきは、現在使用しているシステムが、最新版へバージョンアップ(アップグレード)できるかどうかという点です。
例えばNotes/Dominoの最新版であるv14は、v9やv10など旧バージョンからのデータや機能を引き継げるよう設計されています。アップグレードの方法には、既存のDomino環境にそのまま上書きインストールする方法と、新しいマシンに移行する方法の2通りがあります。
同じサービスラインでのバージョンアップであれば、ユーザーインターフェースや操作性が大きく変わらない可能性があります。
業務フローやアプリケーションもそのまま活用できるため、現場の混乱も最小限に抑えられます。
「なるべく負担をかけずに安全性を向上したい」と考える企業にとって、現実的な選択肢と言えるでしょう。
ただし、アップグレードには新たなライセンスの購入や各端末への導入作業、他システムとの連携確認など、一定の工数とコストがかかる点には注意が必要です。
他のシステムへの移行
現在のサービスラインにこだわらず、自社にとってより適したシステムへ切り替えるという選択肢も有効です。
特に「ハードウェアや周辺機器が老朽化してきた」「最新の技術で業務効率を高めたい」といった課題を感じている場合には、他のシステムに関する情報収集をおすすめします。
近年では技術の進化に伴い、SaaSやPaaSを活用した業務システムが急速に普及しています。
SaaS(Software as a Service)は、ベンダーが提供するソフトウェアをインターネット経由で利用できる仕組みです。
一方、PaaS(Platform as a Service)は、システムを開発・実行するためのプラットフォームをクラウド上で提供するサービスです。
こういったクラウドサービスは導入しやすい反面、「自社独自の業務フローに対応しきれない」「複数のシステムが乱立し、データ管理が複雑になる」といった課題を抱えることもあります。
その課題を解決する手段として注目されているのが、ローコード開発プラットフォームです。業務に合わせたシステムをスピーディーに構築できる点が評価されており、開発工数を従来の10分の1に削減した事例もあります。
「自社に合った移行先を選びたい」「効率的な仕組みに移行したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
Notes移行先を選ぶ際の5つの注意点
Notes/Dominoからの移行を検討する際、目先のコストや導入の手軽さだけでシステムを選んでしまうと、将来的に同じような問題を繰り返す可能性があります。
ここでは、移行先を選定するうえで必ず押さえておきたいポイントをご紹介します。
技術者依存、スキル依存の解消
Notes独自の開発スキル(Notes FormulaやLotusScript)を持つ技術者は、高齢化により年々減少しています。さらに、新たな人材の確保も難しい状況が続いており、システムの保守・改修が特定の担当者に集中しやすくなっているのが現状です。
その結果、属人化が進み、将来的な運用や改善に大きなリスクを抱えることになります。
今後を見据えるなら、より一般的に普及している開発言語や、ローコード機能を備えた、扱いやすいシステムをおすすめします。
開発・保守の効率性
機能追加や仕様変更に柔軟に対応できるか、運用後の保守負担を軽減できるかといった点も重要です。開発や改修にかかる工数を抑え、長期的にコスト効率よく運用可能な仕組みかどうかをご検討ください。
セキュリティ対策
データの暗号化やアクセス制御といった基本的なセキュリティ機能に加え、運用監視や異常検知・自動処理といった機能が備わっているでしょうか。
特に大企業や公共機関では、内部統制や監査対応を見据えた設計かどうかも判断材料です。
サポート体制
トラブルや不明点が発生した際、迅速なサポートが受けられなければ業務が停止してしまうかもしれません。
海外製のサービスでは、時差や言語の違いにより対応が遅れるリスクがあります。
そのため、日本国内にサポート拠点があるか、あるいは日本語でのサポートが可能かをご確認ください。
他システムとの連携性
Notesは他システムとの連携が難しく、情報が分断されてしまう「サイロ化」が起こりやすいのが課題です。また、API連携やクラウドサービスの活用が取り入れにくく、全社的なデータ活用や業務連携を妨げる要因にもなっています。
このような状況を改善するには、他のシステムやサービスと柔軟につながるプラットフォームの導入が欠かせません。
まとめ
Notes/Dominoのv9およびv10は、2024年6月1日をもって通常サポートが終了しましたが、2026年6月2日まで延長サポートが用意されています。ただし、この延長期間はあくまでも猶予に過ぎません。
対応を後回しにしていると、気づかないうちにサポート期限を迎えてしまい、セキュリティリスクの増加や保守コストの高騰、さらにはシステム停止といった深刻なトラブルを招く可能性があります。
こうした事態を防ぐためには、今のうちに準備を進めておくことが重要です。
Notes/Domino v14へのアップグレードという選択肢もありますが、将来の事業成長や業務の変化を見据えるなら、より柔軟なシステムへの移行も検討すべきでしょう。
そこで注目したいのが、自社独自の業務アプリケーションを構築・運用できる「Lakeel DX」です。
Lakeel DXはローコードでの高速開発や効率的な運用管理が可能で、移行後の拡張性や保守性にも優れています。興味のある担当者様は、以下のページから資料をご請求ください。
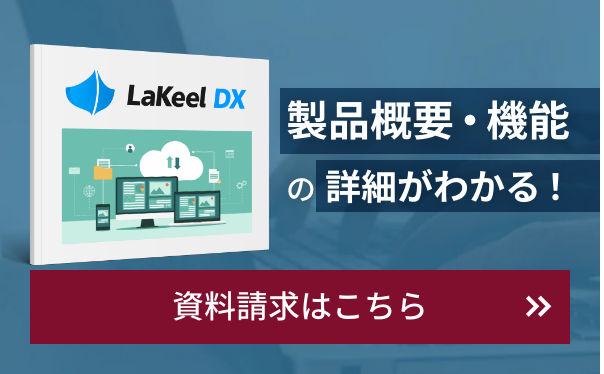
- LaKeelシリーズ サービス資料請求
- ラキールがご提供する「LaKeelシリーズ」について、資料請求をご希望の方はこちらから受付しております。 お気軽にお申し付けくださいませ。
システム移行は想像以上に大きなプロジェクトになることもあります。トラブルを避けるには、計画的な準備と、信頼できるパートナー選びが欠かせません。
当社では「データハブを活用した段階的システム移行」をご提案しています。
いきなり全面移行するのではなく、徐々に切り替えることでリスクや負担を大幅に軽減することが可能です。
以下に、従来の移行手法に潜む課題と、解決策としての段階的システム移行、実際の導入事例をまとめた資料をご用意しました。
「どこから手をつけてよいか分からない」「無理のない移行方法を知りたい」とお考えのご担当者様は、是非ご活用ください。
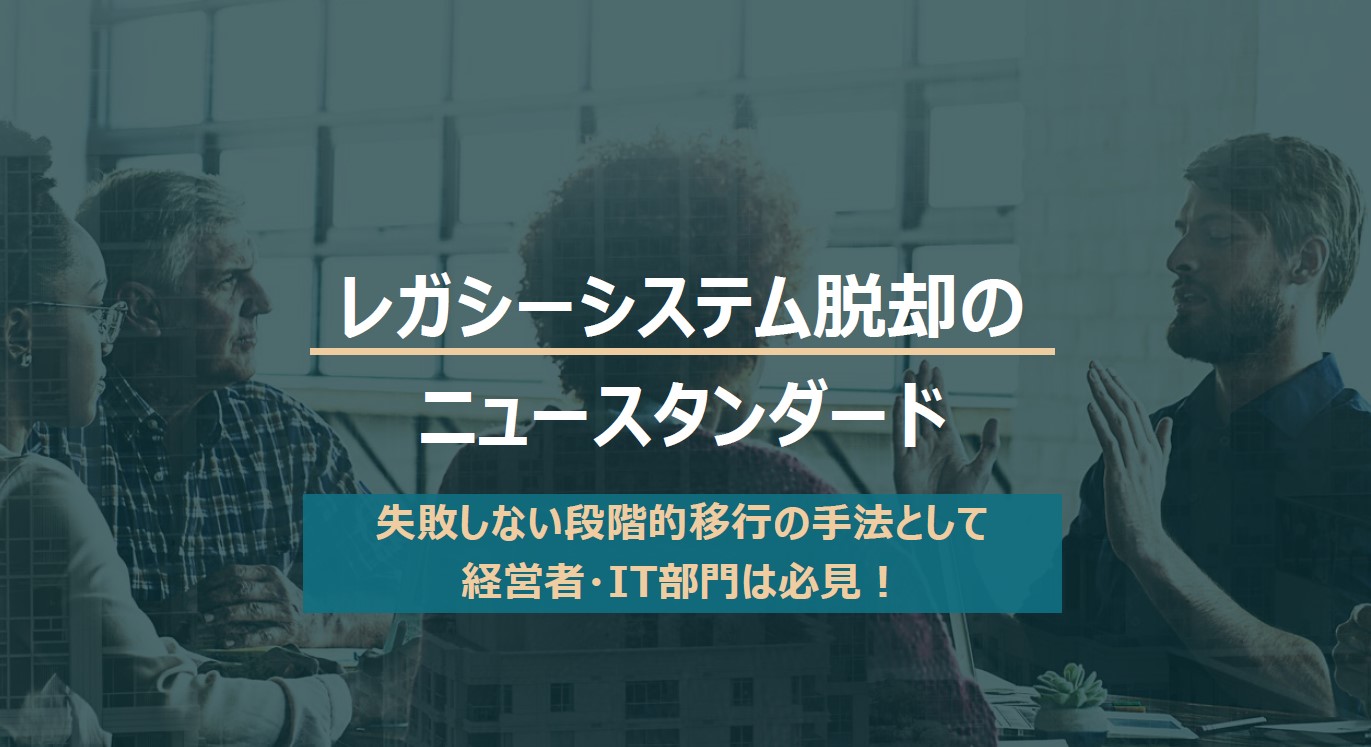
- お役立ち資料
- レガシーシステム脱却の
ニュースタンダード

このコラムを書いたライター

本サイトでは、企業のDX推進に役立つ様々な情報をお届けしています。