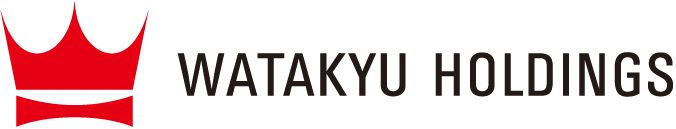クラウドネイティブとは?
アプリケーション開発や運用にもたらすメリットと導入時の注意点

クラウドの特性を最大限活用するクラウドネイティブはシステムの拡張性、柔軟性、可用性を高めるために有効なアプローチです。近年ではDXの推進や新規事業開発に取り組む企業も増えていますが、これらの取り組みにおいてスモールスタートやリリースの高速化を実現しやすいクラウドネイティブは有効な選択肢となります。
今回はこれからクラウドネイティブによりシステム開発を行いたい方に向けて、クラウドネイティブの概要からメリット、注意点とその対策まで詳しく解説します。
- 目次

- お役立ち資料
- スマートに機能を拡張する
「aPaaS」とは
クラウドネイティブとは何か
まず、クラウドネイティブの概要からご紹介します。
クラウドネイティブとは
クラウドネイティブとは、クラウドの特性を最大限に活かせるように、システムを設計・開発・運用するアプローチを指します。
クラウドネイティブを推進する非営利団体「Cloud Native Computing Foundation (CNCF)」では、クラウドネイティブを以下のように定義しています。
| クラウドネイティブ技術は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドなどの近代的でダイナミックな環境において、スケーラブルなアプリケーションを構築および実行するための能力を組織にもたらします。 このアプローチの代表例に、コンテナ、サービスメッシュ、マイクロサービス、イミュータブルインフラストラクチャ、および宣言型APIがあります。 ※出典:CNCF Cloud Native Definition v1.1 日本語訳より |
この定義からも分かる通り、クラウドネイティブは拡張性、可用性、柔軟性といったクラウドの利点を最大限に引き出すために、クラウド環境に加えて関連する技術・アーキテクチャを利用するものです。
従来のオンプレミス環境や、既存システムをそのままクラウドに移行する「クラウドリフト」とは異なり、クラウドネイティブでは最初からクラウド上での稼働を前提とした設計思想に基づきシステムを構築し、クラウドのメリットを最大限享受できるようにします。
クラウドファーストとの違い
クラウドネイティブと混同されやすい概念に「クラウドファースト」があります。クラウドファーストは、新しいシステムを構築する際にクラウドの利用を優先的に検討する方針を意味します。つまり、クラウドファーストとはクラウドを「第一候補」として選ぶ姿勢を指します。
一方でクラウドネイティブは、クラウドで動作することを前提に設計されたアーキテクチャや開発手法そのものを指します。クラウドファーストが「選択の優先順位」であるのに対し、クラウドネイティブは「設計思想と技術実装のあり方」と言えるでしょう。
クラウドネイティブの技術
クラウドネイティブの実現には、以下のような技術が活用されています。いずれも、クラウドの拡張性・柔軟性を最大限に活かせる技術です。
〇コンテナ
アプリケーションとその依存関係を一つにまとめ、どの環境でも一貫して動作させる技術であり、DockerやKubernetesが代表例です。
〇マイクロサービス
アプリケーションを小さな独立したサービスに分割し、それぞれ独立して開発・デプロイを行うアーキテクチャです。
※関連記事:マイクロサービスとは?DX実現へ導入が進む理由とモノリシックアーキテクチャとの比較
〇サービスメッシュ
マイクロサービス間の通信を管理し、セキュリティやトラフィック制御を容易にするための技術です。
〇イミュータブルインフラストラクチャ
サーバーやコンポーネントを変更するのではなく、新しいバージョンを作成して置き換える手法で、システムの安定性と管理の容易性を追求します。
〇宣言型API
最終的に得たい結果を指示することで、システム側が自律的に必要な処理や状態を実現する仕組みです。
〇CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)
コードの変更を自動的にビルド・テスト・デプロイすることで、高頻度でのリリースと品質を両立できる手法です。
使われている場面
クラウドネイティブは、大規模なWebサービスや頻繁に機能追加が求められる新規事業開発などにおいて特に有効です。
〇大規模なWebサービス
アクセス数の変動が激しいサービスでは、クラウドのメリットである拡張性や柔軟性がポイントとなります。自動スケーリングやマイクロサービスによる柔軟な対応が有効です。
〇新規事業開発
市場の変化に迅速に対応する必要があるプロジェクトでは、短期間での開発・リリースが可能なクラウドネイティブが有効といえるでしょう。
〇グローバル展開
複数リージョンでの展開や多言語対応が求められる場合、クラウドネイティブの分散性と自動化が強みとなります。
クラウドネイティブ開発・運用のメリット
クラウドネイティブに基づき開発や運用を行うことには、以下のようなメリットがあります。
IT環境をスピーディーに構築できる
クラウドサービスを活用することで、物理的なサーバーの調達や設置といった工程が不要となり、必要なリソースを即座に調達・構築できます。
クラウドネイティブの考え方に基づきクラウドを最大限活用することで、開発環境や本番環境の立ち上げも迅速化できます。サービスの立ち上げや新機能のリリースまでのリードタイムが大幅に短縮され、ビジネスのスピードに対応しやすくなります。
※関連記事:ビジネスアジリティを向上するためにIT部門が取り組むべきこととは
拡張性に優れている
拡張性に優れたクラウド基盤を活用すれば、アクセスの増加や機能の追加といった変化にも柔軟に対応できます。また、マイクロサービスやコンテナ技術を用いれば、特定の機能だけを個別にスケールさせることも可能です。
このようにクラウドネイティブに基づく設計を行うことで、ビジネスのグロースも進めやすくなります。
コストを最適化できる
クラウドでは一般的に従量課金モデルが採用されており、必要な分だけリソースを利用し、利用した分だけ費用を支払います。これによりピーク時にはリソースを増強し、閑散期には縮小するなど、無駄なインフラコストを抑えた柔軟な運用が可能です。
また、物理的な機器が不要であり初期投資を抑えられる点も、クラウドネイティブの魅力といえるでしょう。
メンテナンスが容易となる
クラウドネイティブでは、アプリケーションとインフラのメンテナンスを切り離せる点もメリットとなります。インフラ側は、クラウドサービス事業者側で運用管理を行うため、利用者側ではアプリケーションのメンテナンスに集中できます。
また、マイクロサービスやコンテナを活用することで、特定の機能やサービスの単位での更新・修正が行えるため、システム全体を停止せずにメンテナンスを実施できます。さらに、CI/CDを組み合わせることで、コード変更の自動反映やロールバックも容易となり、運用負荷も軽減できます。
クラウドネイティブ開発・運用を導入する時の注意点
一方で、クラウドネイティブを採用する際には、以下のような点に注意する必要があります。
セキュリティ範囲の線引きを明確化する
クラウド環境では、「責任共有モデル(Shared Responsibility Model)」という考え方が採用されています。これは、クラウドサービス提供者(CSP)と利用者が、それぞれセキュリティ責任を分担するというものです。
多くのクラウドでは、インフラの物理的なセキュリティやハイパーバイザーの管理はクラウド事業者が担いますが、アプリケーションの設定やデータの保護、アクセス制御などは利用者の責任となります。運用にあたってはこの境界を意識し、自社で行うべきセキュリティ対策の範囲を理解しなければなりません。
特にクラウドネイティブでは、マイクロサービスやAPI連携、サーバーレスアーキテクチャなど、従来の境界型セキュリティではセキュリティをカバーしきれないアーキテクチャが採用されます。ゼロトラストモデルの導入やIAM(Identity and Access Management)の活用など、クラウド特有のセキュリティ対策が求められます。
専門知識・スキルを保有するエンジニア不足への対処を検討する
クラウドネイティブ開発には、コンテナ、マイクロサービス、CI/CDなどの高度な技術スキルが求められます。しかし、これらに精通したエンジニアは市場でも限られるため、人材の確保が課題となります。
クラウドネイティブを実現するためには、フロントエンド・バックエンドの両面でクラウド環境に対応できるフルスタックな人材や、DevOps文化を理解したエンジニアの育成・採用が求められます。社内教育や外部採用に加えて、限られた人材でもクラウドネイティブを実現できるツールの活用も視野に入れるべきでしょう。
クラウドネイティブ型の開発・運用を実現するプラットフォーム「LaKeel DX」
このように、クラウドネイティブを実現するにあたっては、人材不足が一つの課題となります。ここで有効となるのが、エンジニアでなくても実装を行えるローコード・ノーコード開発プラットフォームの活用です。
当社では、限られた社内人員で柔軟にシステムを構築できるプラットフォーム「LaKeel DX」を提供しています。LaKeel DXの以下の特徴により、クラウドネイティブに基づくアプリケーション開発を、限られた人員で実現することができます。
・クラウド型のシステム開発・運用基盤であり、利用状況に応じて柔軟にリソースを調整可能。
・いわゆるaPaaS(Application Platform as a Service)として、ローコード/ノーコードでシステムを開発。エンジニアでなくとも実装を実現できる。
・画面部品とビジネスロジックを分離して構築。それぞれ、マイクロフロントエンド、マイクロサービスとして部品化され、柔軟な機能の組み合わせや再利用、拡張が可能。
クラウドネイティブを実現できるプラットフォームについてご検討されている方は、ぜひLaKeel DXの導入をご検討ください。

- お役立ち資料
- スマートに機能を拡張する
「aPaaS」とは

このコラムを書いたライター

本サイトでは、企業のDX推進に役立つ様々な情報をお届けしています。